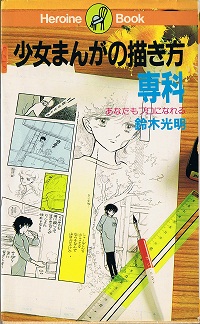|
|
スチュアート・オルソップ『最後のコラム ガン病棟からの回想』崎村久夫訳、文藝春秋、1976年。 (原書 "STAY OF EXECUTION A Sort of Memoir" Stewart Alsop, J. B. Lippincott Co., Philadelphia & New York, 1973)
|
『最後のコラム』という本のことは、『はみだしっ子語録 ── さまよう青春のみちしるべ』
(白泉社ヒロインブック、1981年)の中で、三原順さん自身により紹介されています。
どこへ行こう。どこまで行こう。日ごとボク達は繰り返し……。どこへ? もう行かないのだ……と、心で知る日まで。心で知る日まで……。(「ブルーカラー」グレアム)
*「心で知る」という言葉は、「頭で知る」との対比で、気に入って使ったのですが、
本来の文章では(?)原水爆の使用が禁止されねばならないという事を「頭」で知る事から「心」で知る事への変化として
書かれておりまして…(意味が通じないでしょうか? この説明では)。とにかくあまり関係ないかも知れませんが、
この言葉を拾ってきたのは、スチュアート・オルソップ「最後のコラム」からです。
(『はみだしっ子語録』p.31)
これに限らず、三原順さんが『最後のコラム』から多く引いていることは、
おかのさんのリストをはじめ、
以前から聞いていたのですが、改めて通して読んでみましたのでメモしておきます。
確かに、この本からの引用は多いようです。
スチュアート・オルソップ氏と『最後のコラム』
本の訳者あとがきなどを参考に、著者スチュアート・オルソップ氏の略歴など。
1914年、アメリカのコネチカット州エイヴォンに生まれる。オルソップ家は、
一族から二人の大統領(セオドア・ルーズヴェルト、フランクリン・ルーズヴェルト)を輩出する
メイフラワー号時代から7代を重ねた東部エスタブリッシュメントの名門。
1936年、エール大学卒業。英陸軍に志願(後に米陸軍)、特別空挺隊員としてフランス出撃直前、
ロケット攻撃下のロンドンで結婚。
1946年、既にコラムニストであった兄と共同でニューヨーク・ヘラルド・トリビューン系のジャーナリストとなる。
サタデー・イブニング・ポスト誌で独立後、1968年にニューズ・ウィーク誌へ。
1971年、白血病の診断。闘病生活の後、1974年5月26日他界。享年60歳。
本書中でも、ニクソン大統領(1971年当時、現職)から病室に見舞いに行こうかと電話があったエピソード(p.66)をはじめ、
ヘンリー・キッシンジャーとしばしば昼食会をもっていたことや、チャーチルとのエピソードなど、
ジャーナリストとしては妙に恵まれていた環境と想像します。
訳者あとがきによると、「ハト派とタカ派」というのは、スチュアート・オルソップの造語だとのこと。
どうやら、1966年にスチュアートがサタデー・イブニング・ポスト誌に書いた記事のようです
("Mr. Dove and Mr. Hawk", Alsop, Stewart, The Saturday Evening Post, June 18, 1966, Vol. 239 Issue 13, p18)。
『最後のコラム』は、1971年7月に白血病と診断されてから、1973年5月にかけてのコラム集となっています。
典型的な急性白血病と異なる独特の症状で医者と本人を悩ませながら、いったん回復の兆しを見せ、
再び悪化する2年間の、病状や思い起こしたさまざまなことのエッセイになっています。
原題の"Stay of Execution"は、訳者あとがきによれば、本来は法律用語で刑の一時停止を意味するとのことです。
つまりすべて、死を宣告されながら、一時停止によって、検査結果に向き合い怯えながら生き続けた
状況下での文章になります。
 |
|
三原順『はみだしっ子』「バイバイ行進曲」より (白泉社文庫第3巻P379、花とゆめコミックス第7巻P109)
|
第1部
1971年7月、著者の体調の異変が、白血病と診断されます。
姉と私が病気になったとき、母が聖ペトロに願い出て「少々神様とお話したい」と頼んだというのは、
そういうわけで、いかにもありそうな話だった。
姉がこの話をしてくれて以来、私は死の恐怖に襲われるたびに、
こんな祈りの言葉を唱える習慣ができた。
「お願いですお母さん、
お願いです神様」
後になって、今は天国にいる私の愛した二人の人物をこれにつけ加えた。父と、病弱だった幼年時代に世話をしてくれた
スコットランド生まれの看護婦アギー・ガスリーである。かくして、祈りの文句はこんなふうにおさまりがついた。
「お願いです神様、
お願いですお母さん、
お願いですお父さん、
お願いですアギー」
(『最後のコラム』「訳者あとがき」p.39〜40、太字は立野による(以降、同様))
本書の中でオルソップ氏は、自分は不可知論者だと書いています。
「私は、不可知論者である。無神論者ではない。神はいないと言っているのではなく、
神がいるかどうかはわからないと言っているだけだ。たしかに、神秘はどこかにひそんでいる」(『最後のコラム』p.172)。
そんなオルソップ氏の祈りの言葉は、上記のようなもので、本書の中で繰り返し使われています。
そして、『はみだしっ子』の中で、グレアムの祈りの言葉は、こんなふうです。
お願いです神様
どうぞアンジー
どうぞサーニン
どうぞマックス
お願いです
(「バイバイ行進曲」、白泉社文庫第3巻P379、花とゆめコミックス第7巻P109)
 |
|
三原順『はみだしっ子』「奴らが消えた夜」より (白泉社文庫第3巻P41、花とゆめコミックス第5巻P135)
|
オルソップ氏は、初めての血球値測定で、死ぬ寸前であったほどヘモグロビン値が低かったことがわかります。
このときのヘモグロビン値についての文章は、「奴らが消えた夜」でアンジーがネタにしています。
ヘモグロビンは、エネルギーと
生命の躍動と
生きる喜びを与えてくれる。
ヘモグロビン値が高ければ(つまり赤血球が多ければ)、山へ登ったり女の子を追っかけたりしたい気分になる。
「思考力なく、薬一服と酒への強い欲望」とは、
G・K・チェスタトーン(イギリスの随筆家、批評家、小説家。1874-1936)の
叙事詩的二行連句だが(それともヒレア・ベロック(イギリスの随筆家、詩人、批評家。1870-1953)だったか)、
これはヘモグロビン値の低いときに人が感じる気持をうまく要約している。
(『最後のコラム』p.43)
こんなふうに、『最後のコラム』全体を通して、オルソップ氏は深刻な病状を詩的エッセイにしています。
白血病と診断された自分に、周囲が優しかったことは、次のように綴っています。
ほかにもいろんな走り書きがある。手帳の半ばあたりまでめくると、ページのいちばん上に、
「白血病」という言葉が書いてある。
これは、7月21日の朝、つまりペリー博士から病気の宣告を受けた翌日、書いたものだ。
走り書きは、もう少し続いている。「みんな、どうして、こんなに優しいのか。
神は毛を刈られた仔羊には風を加減したまう――古い文句だ――突然、まざまざとその光景が目に浮かんだ――
『恐ろしき死がわが心をかき乱しぬ』――『かき乱しぬ』とは、まさにぴったりだ――罪の許し――」
(『最後のコラム』p.53)
「神は毛を刈られた仔羊には風を加減したまう」という言葉は聖書からの引用だと思っていたのだが、
バートレット引用語辞典で調べてみて、ローレンス・スターン(イギリスの作家。1713-68。
紀行「センティメンタル・ジャーニー」中の文章)の言葉だとわかった。そして、
「突然、まざまざとその光景が目に浮かんだ」のであった――毛を刈られた仔羊が寒風にさらされている光景。
それが私自身なのだ。そのうち自己防衛の心理作用が働きはじめ、
それにつれて風は熄み、なんとか耐えられるようになる。
(『最後のコラム』p.55)
「神は毛を刈られた仔羊には風を加減したまう」は、『はみだしっ子』番外編「G・A・S・Mのお料理教室」で
出てきますよね(白泉社文庫第3巻、花とゆめコミックス第7巻)。お料理教室には、他2つの引用が『最後のコラム』から
とられたものであると思われます(後述)。
 |
|
三原順『はみだしっ子』「窓のとおく」より (白泉社文庫第3巻P280、花とゆめコミックス第7巻P12)
|
『はみだしっ子』の中では、グレアムの父が(おそらく)癌で死んでいくところで、
『最後のコラム』の引用がいくつか重ねられます。「窓のとおく」でグレアムは、
滑稽詩で父の不治の病をイメージさせますが、この詩は『最後のコラム』から取られたものと思われます。
オルソップ氏は、自分の状況を滑稽詩になぞらえて書いています。
滑稽詩もいくつかあった。私はこういう詩が好きなのである。ベロックの「戒め物語」から、
ヘンリー王の悪い癖、
ひもをくちゃくちゃ噛むことよ。
とうとう、ちょっぴりのみこんだ、
でっかい結び目あるやつを。
一番名高いお医者たち、
すぐに召されてやってきて、
料金もらって言うことにゃ
「この御病気はなおりません」
さらにおなじみのクラレンス・デイ(アメリカの随筆家。1874-1935)がある
(私は、これをジェームズ・サーバーの文章だと勘違いし、おまけにすっかり間違えて記憶していたが、
弟のジョンは私よりずっと優秀な記憶力の持主で、私の勘違いを直してくれた)。
さらば、私の友たちよ――
さらば、となえよ、ばんざいを!!
聖林さがしにわたしは行こう、
なぜかはわたしも言えないが。
おぼえておいて、おねがいだ、わたしが去ったのちまでも、
わたしを動かすこの大志。
チータカタッタ、ピーヒャララ、
君らといっしょにいたいんだ、
けれど、ここらで、さようなら。
こうやって思い出すものの内容からも、私の憂鬱な気分がはっきりうかがえる。
私のおぼえている引用句などさやかなものではあるが、それをあれこれ思い出そうとつとめていると、奇妙に心が慰められた。
いわば、自分の不幸の上に壁紙を貼って隠しているようなものだった。
(『最後のコラム』p.71-72)
 |
|
三原順『はみだしっ子』「窓のとおく」より (白泉社文庫第3巻P276、花とゆめコミックス第5巻P8)
|
クラレンス・デイの「チータカタッタ、ピーヒャララ」のところも、「窓のとおく」でフー姉様の台詞で出てきますよね。
オルソップ氏は、彼自身書いているように、こんな引用句を思い出してみることで、
平穏を保とうとしていたところもあるようです。
第2部
 |
|
三原順『はみだしっ子』「バイバイ行進曲」より (白泉社文庫第3巻P364、花とゆめコミックス第5巻P94)
|
1971年9月、オルソップ氏の体調は、不思議な回復を見せ始めます。
それは、その年の暮れくらいまでの束の間の栄光の日なのですが、
検査の結果を聞いたオルソップ氏は、
自分は信心深くないが、教会に行って祈りたい気分になったと書いています。
私は、ちょっとバツのわるい思いで、以前グロートン校のチャペルでやっていたように、手と手の間に顔を伏せ、
「主の祈り」を唱えた。私にとって、神が大きなひげを生やした現実的な存在であったあの日々のように、
私は口早に祈りの文句を唱えた。「我らの日用の糧を日毎に与へ給へ。我らに負債ある凡ての者を我ら免せば、
我らの罪をも免し給へ」ここまできて私はつかえた。最後の一行がどうしても思い出せないのだ。
こうして祈っている間も、なにか不自然なことをやっているときに(おそらくだれしも)感じる、間の悪さが続いていた。
白血病という異常な体験によって、私が深い精神的な洞察力を得たと言うことができたらどんなに嬉しかろう。
しかし、事実はそうではなかった。子供のころのあの偉大なひげを生やした存在は、もはや私にとって現実性を失っていた。
かすかなぎこちなさは、そのためだった。私は十八才ごろから不可知論に傾き、今もなお不可知論者なのである。
(『最後のコラム』p.171-172)
この、「主の祈り」の最後の一行が思い出せないというエピソードは、
「バイバイ行進曲」の中で使われています。
1972年になるとオルソップ氏の病状は再び悪化し、
2月には、末期がんだった古い友人のトミー・トムスン氏が亡くなり、彼の文章も重苦しくなっています。
『はみだしっ子』番外編「G・A・S・Mのお料理教室」の「人間の人間に対する非人間的なむごさ」という引用は、
『最後のコラム』で以下のように出てきます。
ロバート・バーンズ(スコットランドの詩人1759-1796)は、「人間の人間に対する非人間的なむごさ」という
句を残している(バートレットの引用句辞典にあたってみるまで、私はてっきりアレキサンダー・ポープの詩句とばかり
思いこんでいた)が、自然の人間に対する残酷さについて書く人はほとんどいない。しかし、自然の残酷さが
その頂点に達するとき、それは人間のやってのけるむごい仕打ちの比ではない。
(『最後のコラム』p.252)
オルソップ氏は、人間の酷さのために引用しているのではありませんでした。
死を待つ人々の病院で、酷い姿の病人をあまりに多く見たオルソップ氏は、
自然の――病気の――凄まじい酷さを前に、「実際、神の正義と慈悲がこの世のどこにあるのか」と書きます。
神なるものが存在するとしても、その神は、愛によってよりも、むしろ恐怖によって万物を統治する、
残忍にして、何をしでかすかわからない神にちがいあるまい。昔、ラテン語の四年次用教科書で習った
次の句がひょいと記憶に甦ってくる。――「この世に神々を創出したのは恐怖である」(スタティウス「テーバイス」)。
まさしく人間の心には、冷静な理性、偏見のない不可知論の層の下深く、恐怖が埋まって存在している。
われわれ人間は、万一の場合を考えると、とうてい存在しそうにないものにまですがりつきたくなるのである。
ルーレットのゼロゼロの目にチップを一枚張るのである。どうか、神さま! お母さん! お父さん! アギー!
トミー・トムスンが死んだせいで、私は気が滅入ってしまったようだ。
(『最後のコラム』p.255-256)
ルーレットのゼロゼロというネタは本書でこの前にも使われていて、
「ゼロゼロは親の総取り。客がこの目に張ることはありえない」と訳注されています(『最後のコラム』p.189)。
『はみだしっ子』番外編「ついに嫌われたMの大冒険」のオチに使われていますよね
(白泉社文庫第3巻、花とゆめコミックス第7巻)。
第3部
日記風であった第2部と違って、第3部は少しまとまった文章が書かれています。
その中に、オルソップ氏が肺炎で熱を出して入院した際に、
偶然彼と同室になった白血病患者レコジ氏の話がありました。
この青年は、レコジ・アンジャインという耳なれない名前だった。マーシャル群島の生まれなのだった。
1954年、われわれアメリカ人が、マーシャル群島のビキニ環礁で初めての水爆実験を行なったとき、
レコジはまだ一歳だった。
(『最後のコラム』p.328)
 |
|
三原順『はみだしっ子』「ブルーカラー」より (白泉社文庫第4巻P323、花とゆめコミックス第9巻P109)
|
ビキニ水爆は、この計画を担当したエドワード・テラーたち科学者の予想をはるかに超える強力なものだった。
そればかりか、予想もしていなかったことが起きた。爆心地で厖大な量の土が激しくかきまわされ、微細な土埃と化して、
大量の放射能を含んだ塵が風に乗って各地へ降下したのである。その一部は、爆心から90マイル以上も離れていた
日本のマグロ漁船第五福竜丸の上にも降り注いだ。乗組員の全員が放射能障害にかかったが、耳にするかぎりでは、
その中で白血病で死んだ者はいない。(1954年9月23日、第五福竜丸無線長久保山愛吉が「放射能症」で死亡している)
放射能灰はマーシャル群島のほかの島々にも降下した。ビキニから百マイル以上離れたロンゲラップ島もその一つだった。
島々の住民たちは放射能に冒された。このロンゲラップ島が、レコジ・アンジャインの故郷なのである。
私の脳裡には、いまだにこんな光景がこびりついて離れない。元気のいい褐色の肌をした赤ん坊のレコジが、
ロンゲラップの椰子の下で遊びたわむれている。と、突然、ビキニの大爆発の閃光が空を貫く。そして、
なにも知らずに遊び続けるレコジの上に、あの放射能の灰が降り注いでくる。この元気な褐色の赤ん坊が、
今、私と同室に横たわっている19歳のレコジ青年なのである。ジョン・グリックの話では、レコジはきわめて悪性の
急性骨髄性白血病だということだった。
(『最後のコラム』p.328-329)
オルソップ氏が退院して10日後にレコジ氏が亡くなったと電話があり、死因は肺炎。
「でも、ご自分のせいだなどとお考えになっちゃいけませんわ」
ともあれ、レコジの死に私はいくばくかの責任があるという沈んだ気持は拭いきれなかった。
さらに、われわれアメリカ人のすべてがレコジの死に責任がある――われわれが水爆でレコジを殺したのだ、
という思いも消えなかった。レコジは世界で初めての水爆犠牲者である――そして、その水爆はアメリカの水爆だった。
なによりも、あの穏やかで妙に無邪気だった若者が死んでしまうなんて、なんと悲惨な、不当なことだろうという思いがした。
あるとき、こんな詩句が私の心に浮かんだ(手許にないが、T・S・エリオットだと思う)。
――かぎりなく優しきものの思いよ かぎりなく続く悲しみよ――。
レコジが死ぬ前からずっと、私はこんな信念を頭の中に持っていた
――核兵器は、見さかいのない、想像を絶した残忍な兵器である。それは狂気の兵器であり、人類を自滅に導く。
断じて人間の手にすべきものではない、と。今、私は、それを心で知ったのである。
(『最後のコラム』p.328-329)
これが、三原順さんが『はみだしっ子語録』の中で触れていた箇所です。
 |
|
三原順『はみだしっ子』「バイバイ行進曲」より (白泉社文庫第3巻P381、花とゆめコミックス第5巻P111)
|
最後のコラムは、こんな文章で終わります。
「眠い人には睡眠が必要なように 死にかけている人には死が必要なんだ……」は、
「バイバイ行進曲」のグレアムの台詞で、チャーチルの言葉は、
『はみだしっ子』番外編「G・A・S・Mのお料理教室」で使われています。
だが、あの土曜日、私が恐怖でとり乱さなかった最大の理由は、いわく言いがたい不思議な心理プロセスが知らず知らずに
進行していたためだと思う。この本の中で、なんとか表現しようとしてきたことだが、それは人が死と折り合いをつけてゆく
適応のプロセスなのである。眠い人間に眠りが必要なように、死にかけている人間には死が必要である。
そのときがくれば、逆らうのは無益だし、まちがっている。
病いにたおれた初めのころ、私はチャーチルのとあるエピソードをよく思い出した。
それは、晩年のチャーチルが母校のハロー校を訪れたときの有名な話である。
生徒たちに一言お願いしたいと校長に乞われて、チャーチルは言った。
「断じて諦めるな。
断じて、
断じて、
断じて、
断じて!」。
なみはずれた努力となみはずれた意志によって、この老人が寿命より長生きしたことは疑いない。
チャーチルは諦めなかったゆえに長生きした。しかし、それがどんないい結果を生んだというのだ。
(中略)
人間には生きるべき時がある。しかし、同様に、死すべき時がある。私には、まだその時は訪れていない。
が、いずれその時がくる。何ぴとにも、その時はくる。
(『最後のコラム』p.353-354)
『おごそかに死ぬ権利』
本書の文章から約一年後に、正確な病名が決まらぬまま、三回の開胸手術の後、オルソップ氏は亡くなります。
「訳者あとがき」によると、絶筆となったコラム『おごそかに死ぬ権利』について、以下のように解説されていました。
看護婦によれば、当節のアメリカ人には珍しく、最後まで絶対に泣きごとを言わぬ患者だったというが、
死後、グッド・ハウスキーピング誌(1974年8月号)に発表された絶筆『おごそかに死ぬ権利』によると、安楽死を提案している。
白血病棟から、病院側の都合で12W号棟(西棟12階、固形腫瘍病棟)に移されたオルソップは、
極度の苦痛にうめきながら死を待つだけの患者が次々と運び込まれてくるのを見て、
「苦痛も生命の一部であり、故に苦痛からのがれようとするのは罪である」というピューリタン的な倫理に
疑問をいだくに至る。そして、自己の理性を統御できる状態にある癌患者は、経験豊かな医師からなる委員会にはかって、
もしその病いが不治であり苦痛が死ぬまで続くことがわかれば、自殺用の薬品を受け取る権利を認められるべきだ、
と言うのである。そして、「だが、その権利は患者自身のものであって、医師のものではない」と書く。
また、人間は、そうは思っても、最後の瞬間には「生」にしがみつく。また、自殺が神の意志に反するという
宗教的信念もあろう。そのような場合には、ヘロインを用いて苦痛を除くと同時に、つかの間の喜びを味わわせながら、
徐々に死なせてやってもいいのではないか、とも言う。この理屈が正しいかどうかは別にして、
この文章を書くにいたったオルソップの心中を思うと、訳者は胸が痛む。
(『最後のコラム』「訳者あとがき」p.358)
補遺
『最後のコラム』には、色々なネタがありすぎまして、いくつか補足です。
『はみだしっ子』番外編「Part18とPart19の間」で、
「"ジャック坊やへ" "フレッドおじさんより"」というのがありますが、
もしかすると次の「フレッドおじさんの春」から取っているのかも知れません。
弟のジョンが、P・G・ウッドハウスの「フレッドおじさんの春」を送ってきた。
兄のジョーからはアンソニー・トロロープの「公爵の子供たち」が届いた。
ウッドハウスもトロロープも昔から好きで、どちらも前に読んだことがあるが、
両者とも再読三読にたえるすばらしい作家である。
(『最後のコラム』p.32)
スチュアート・オルソップ氏は、本書の中でスチュウという愛称で呼ばれているのですが、
スチューと聞くとどうしても『ルーとソロモン』「はばたけ光の中へ!」で
「スチューをシチューにして」と言われていたスチュアート君を思い出してしまいます。
これは関係ない気のせいと思いますが、彼の息子が書いた「魔法の森」という小説は、
なんとなくジョディの森を連想させます(『最後のコラム』p.229)。
そして、以下のようなオルソップ氏の思いが、少しだけ『はみだしっ子』番外編「オクトパス・ガーデン」で、
「041号は手塩にかけて育てたエスタブリッシュメント・ペンギンでした」と繋がらなくもない気がしました。
ベトナム戦争は、ワスプ勢力の自信喪失のプロセスに止めをさした。いまやアメリカには、
「支配勢力」と
呼ばれるべきものはなくなった。なくなったほうがいいのかも知れない。が、私にはそうとも言いきれないものがある。
大国は、エスタブリッシュメントを、エリートを、そして自己の利害を超越して物事を処理する能力にたけた人たちから成る、
自信に満ちた階層を必要とするのではないか、と思うからである。
(『最後のコラム』p.196)
まとまりきっていませんが。
(2014年5月 立野昧)